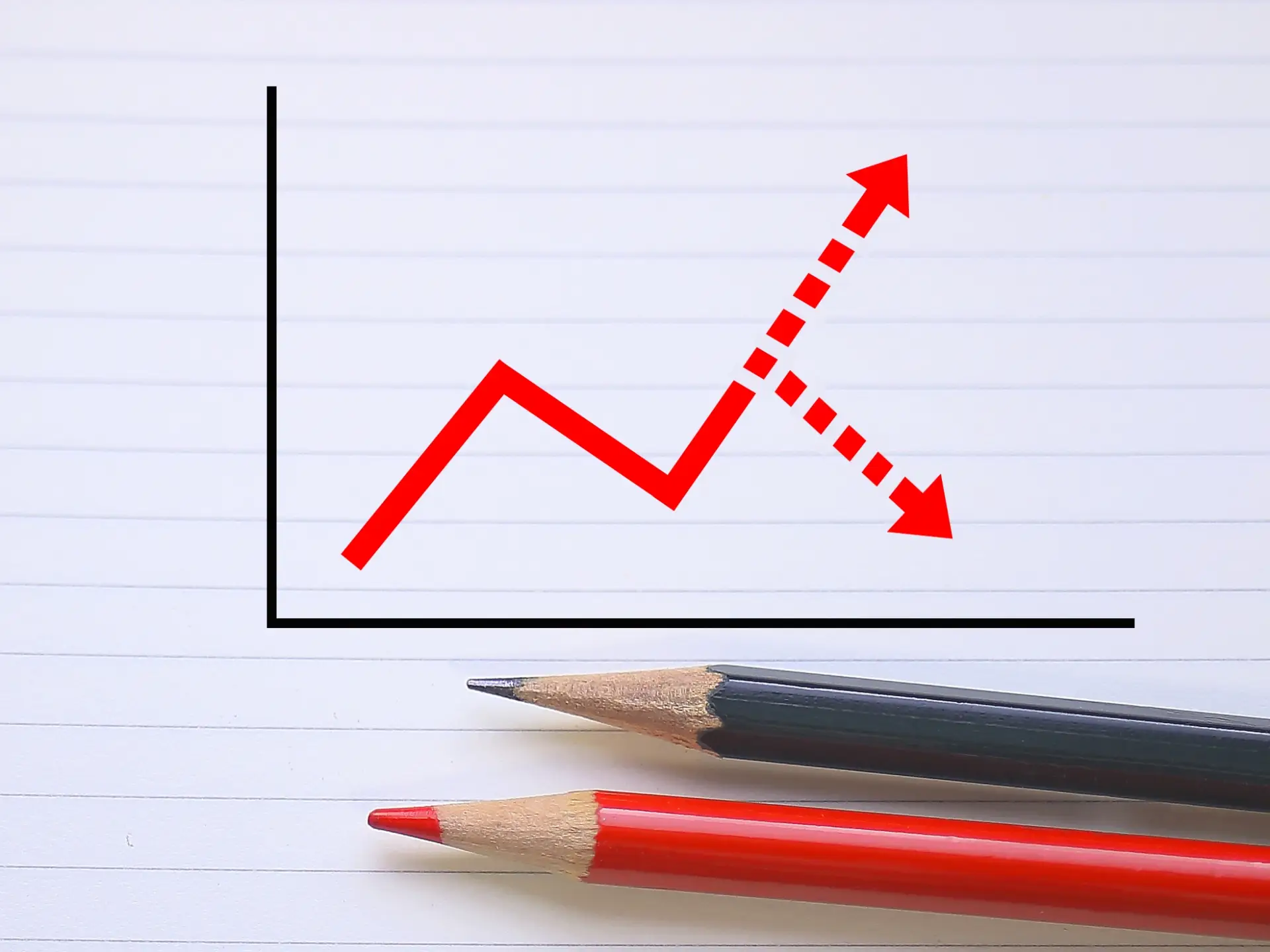やらされ感が若手の成長を止める │ やってみたいを引き出すリーダーシップ術

「自分で考えない若手」に、いつから悩んでいただろうか?
「最近の若い子って、自分で考えないよなぁ……」
そんな言葉が、職場で誰かの口からこぼれる瞬間に、あなたも何度か立ち会ったことがあるのではないでしょうか。
もしかすると、それを口にしたのは、他でもないあなた自身かもしれません。
先日、ある製造業の課長さんと話をしていたときのことです。
彼はこう言いました。
「やる気がある子もいるんですよ。でも、みんな“答え”を求めてくるんです。自分で考えて行動する前に、“これは正解ですか?”って聞いてくる。なんかね……、もったいないなって思うんです」
その言葉に、私は深くうなずきました。
そして同時に、こんな問いを自分に返しました。
「自分で考える」って、実はとても難しいことなんじゃないか?
私たちは、大人になるにつれて「考える力」を身につけてきたように思います。
しかし、その力は決して自然と育つものではなく、誰かに見守られながら、小さなチャレンジとフィードバックを繰り返すなかで、ようやく芽吹くものなのです。
にもかかわらず、私たちはつい“今の若手”に対して、「最初から完成された思考力」を求めてしまいがちです。
彼らに「もっと自分で考えて動いてほしい」と思うのは、当然のこと。
でもその前に、「考える土壌」を、私たち大人が耕せているかどうかを、振り返る必要があるのではないでしょうか。
「答えを求める若手」と「質問を投げ返す上司」
研修や企業内のセッションを通じて、私は数多くの若手社員と接してきました。
彼らが口にする言葉の多くは、
「これ、どうやったらいいですか?」
「正解は何ですか?」
「正しくできてますか?」
という“確認”の問いです。
これは決して、無気力からくる発言ではありません。
むしろ、彼らは
「間違いたくない」
「叱られたくない」
「評価を下げたくない」
という防衛本能のもとに慎重に行動しているのです。
それに対して、
「いいからまず考えろよ」
「俺の若いころは自分で調べたぞ」
と言ってしまえば、彼らの心の扉は、ますます閉じていきます。
今の若者が“思考停止”に陥っているのではなく、「安全や品質に思考する環境がない」だけなのかもしれません。
考えるという行為は、リスクを伴います。
だからこそ「安心できる場」が必要です。
「自ら考えること」は、安心の上にしか成り立たない
私の講義では、最初に「挨拶ワーク」を取り入れることがよくあります。
大きな声で、相手の目を見て、しっかりと「おはようございます!」と伝える。
一見、単純なこのワークに、驚くような変化が現れることがあります。
最初は、恥ずかしそうだった若手たちが、3回目には自然と笑顔になり、ペアの相手の反応に小さくうなずく。
場がゆるみ、安心感が広がったとき、不思議と彼らの発言が変わっていくのです。
「こういうやり方ってどうですか?」
「今のプロセス、ちょっと気になる点があります」
「もしかして、こっちの方法のほうが効率的じゃないでしょうか?」
そう、まるで別人のように、「自分で考えた言葉」を話し始めるのです。
これは偶然ではありません。
人は“安心できる場”にいなければ、自分の考えを外に出すことができないのです。
まるで、冬の間は固く閉じていた蕾が、暖かな陽射しを浴びて、そっと開き始めるように。
「考える力」は、環境が育てるものなのです。
なぜ私たちは、“できる前提”で接してしまうのか?
あなた自身も、かつては新人で、何もわからないところからスタートしたはずです。
それでも、少しずつ「考える力」を育んできたのではないでしょうか。
では、なぜ私たちは、いつの間にか「最初からできていること」を前提に、若手に接してしまうのでしょうか。
それは、自分自身が「できるようになった過程」を忘れてしまっているからかもしれません。
だからこそ、私たちは「考える力」を“教える”というよりも、「思い出させる・再現する・再び体験させる」ことが大切なのです。
若手が考えるようになるには、まず「考えていいんだ」と、感じられる関係性と空気感が必要です。
そして、それをつくれるのは、他でもない私たちリーダーや育成者の役割なのです。

では、私たちは何から変えればいいのか?
ここで、あなたにひとつの問いを投げかけさせてください。
「あなたは、部下や後輩が“考える前”に、つい“答え”を与えてしまっていませんか?」
もしその問いに少しでも心が動いたのなら、きっとあなたは、部下や後輩の“芽”を育てることのできる人です。
その“芽”を伸ばすために、私たちの組織が、知らず知らずのうちに失ってしまったもの、
つまり「バランス」について、もう少し深く掘り下げてみたいと思います。
きっと、あなたの中にある「気づき」の種が、またひとつ芽を出すはずです。
お話しを続けましょう。
バランスを失う組織、「技術偏重の副作用」
「自分で考えない若手」の背景にある環境や関わり方についてお話ししました。
では、なぜ私たちの組織は「若手が育ちにくい場」になってしまったのでしょうか?
その理由の一つに、私は「技術偏重」という、静かで深刻な副作用があると私は考えています。
技術が成長すると、人が成長しにくくなる?
ちょっと、想像してみてください。
ある大手製造業の工場に、設備の異音を察知する“匠の耳”を持ったベテランがいました。
彼は、機械が奏でるほんの小さなズレを聞き分けて、早期の不具合対応をしていたのです。
けれど数年後、センサーがその役割を担い、音の変化はAIによって分析されるようになりました。
技術は進化し、ラインのトラブルは減少しました。
けれど、そのベテランのような「耳を持った人」は、もう育たなくなったのです。
技術は進歩すればするほど、人の「感じる力」「気づく力」「考える力」が置き去りにされる危険性があります。
その結果、「技術はあっても、人が育たない組織」が生まれてしまうのです。
スキルを教えるのに必死で、「人」を見ていない
ここで、少し苦い実話をご紹介します。
ある研修の初日。
リーダー層が一同に集まり、若手の早期戦力化をテーマにしたセッションが、始まりました。
ところが開口一番、ある参加者がこう言ったのです。
「正直、スキルさえ教えておけばいいと思ってます。今の子たちは考えるのが遅い。だったら、やるべきことを手順化して渡せば済むんじゃないですか?」
あなたは、この意見をどう感じますか?
たしかに効率は良いかもしれません。
でも、その“手順”をなぜそうするのか、なぜそれが大事なのかを説明できる人がいなくなったら?
応用や変化が起きたときに、誰が現場を判断し、守るのでしょうか?
私はこのとき、「スキル教育だけでは、人は育たない」という強い危機感を抱きました。
スキルとは“手段”であって、目的ではありません。
本来、組織が育てるべきは「考える人」であり、「成長する人」なのです。
技術偏重とは、“水を張らない田んぼ”のようなもの
ここで、少し風景を思い浮かべてみてください。
広がる田んぼに、農夫が種もみをまいています。
でも、田んぼには水が張られていません。
地面は乾ききり、種はやがて干からびてしまいます。
水――それは、安心・関係性・承認・会話といった、人の成長を支える“栄養”のようなものです。
どれだけ良い品種の種(=スキル)をまいても、土壌(=職場環境)が整っていなければ、芽は出ないのです。
ところが、今の多くの組織では、「スキルは教えたんだから、育って当然」と言わんばかりに、“水を張る”ことを忘れてしまっているのです。

技術重視の裏側で、失われているもの
技術偏重が進む組織で、じわじわと失われていくものがあります。
たとえば
・雑談
・相談する勇気
・「なんか違和感がある」と言える雰囲気
・成長を喜ぶ文化
・お互いの成功を称える関係性
これらは、組織にとって一見“余白”のように見えます。
でも、この“余白”こそが、創造性や自律的な判断力を支える、「土壌」そのものなのです。
技術的には最適解があっても、人間関係や現場対応には、“最適解がない”という場面が多々あります。
そのとき、現場を救うのはマニュアルではなく、「人と人のつながり」と「気づく力」なのです。
「うちの若手はダメだ」と思う前に、自分の空気を点検する
「最近の若手は、報連相すらできない」
「なんで自分で考えないんだ」
そう感じたときこそ、一度立ち止まって、自分の関わり方や組織の空気感を点検してみてほしいのです
相談したくなる雰囲気があるだろうか?
間違えても許される、安心感はあるだろうか?
小さな変化や挑戦に対して、承認の言葉をかけているだろうか?
若手は、やる気がないのではありません。
“やる気が出る仕組み”が整っていないだけなのです。
テクノロジーと人間性、両方があってこそ「育つ組織」
私は、技術の発展を否定するつもりはありません。
むしろ、それによって仕事が進化し、効率が上がるのは素晴らしいことです。
でも、それと同時に、人間性・関係性・対話の文化を手放してはいけないのです。
「高性能なシステムが整っていても、最後に判断するのは“人”」
「マニュアルはある。でも、現場を動かすのは“人の気持ち”」
この2つの視点を、組織の両輪として回していく必要があると考えています。
「考える力を引き出すスイッチ」は、脳の中にある
では、どうすれば若手が「自ら考え、動き出す」ようになるのでしょうか?
それを支えるのが、脳科学的に見た“ドーパミン”と“自己効力感”です。
ドーパミンは、私のコラムの中に多く“出席してくれる”脳内ホルモンです。
ここからは、実際の研修現場で見られた変化の事例とともに、「やらなきゃ」から「やってみたい」へと変わる瞬間について、お話しします。
あなたの中にある「育てる力」のスイッチも、きっと同時にオンになるはずです。
人が自ら動き出す「ドーパミンと探求心」のスイッチ
「うちの若手、やる気がないわけじゃないと思うんです。…ただ、スイッチが入っていないだけのような気がして」
以前、研修で出会った管理職の方が、ふとこんな言葉をもらしました。
そのとき私は、静かにうなずきました。
なぜなら「スイッチが入っていない」という感覚は、まさに行動科学と脳の仕組みで説明できることだからです。
やる気がないのではなく、やる気が出る順番や条件が整っていない。
これは、決して性格や世代のせいではありません。
人間の脳の仕組みが、そうなっているのです。
それでは、若手や部下が「自ら動き出す」ために必要な“脳のスイッチ”、つまり「ドーパミン」と「自己効力感」の正体と活かし方について、やさしくお話ししていきましょう。
行動の裏には、ドーパミンという“やる気の燃料”がある
まず、ひとつ質問です。
あなたが、「よし、やってみよう!」と前向きに行動を起こしたとき、脳の中で何が起きているか、ご存じですか?
そう、そのとき分泌されているのが、「ドーパミン」という神経伝達物質です。
ドーパミンは、期待・予測・報酬といった感情に関わり、私たちを「動かす」力を持っています。
特に、「うまくいきそう!」と感じたときや、「やってみて良かった!」と実感したときに、多く分泌されます。
つまり、人は「できそう」や「おもしろそう」という気持ちを持てると、自然と行動したくなるのです。
逆に言えば、「どうせ無理」「また怒られるだけ」「面白くない」と思った瞬間、ドーパミンは分泌されず、行動意欲も湧かなくなります。
自己効力感があるかないかで、世界の見え方は変わる
では、その「できそう!」という感覚は、どこからくるのでしょうか?
ここで登場するのが、「自己効力感(self-efficacy)」です。
自己効力感とは、「自分にはそれを達成する力がある」という感覚のこと。
もっとわかりやすく言えば、「やれる気がする」という“根拠なき自信”です。
この自己効力感があると、
・失敗しても立ち直りが早くなる
・難しい課題にも挑戦しやすくなる
・周囲に良い影響を与えるリーダーシップが育つ
というように、非常に多くのプラス効果が確認されています。
一方で、自己効力感が低い状態では、
・指示がないと動けない
・「どうせ無理」が口ぐせになる
・ちょっとしたミスで落ち込みやすい
というように、自信が持てず、行動も小さくまとまりがちになります。
だからこそ、「やらせる」のではなく、「やってみたくなる空気」をどう作るかが、重要になってくるのです。
「やってみたら、ちょっと楽しかった」その経験がドーパミンを呼ぶ
では、ドーパミンや自己効力感を引き出すには、どんなアプローチが有効なのでしょうか?
ここで、ある研修現場のエピソードをご紹介します。
ある企業で、若手社員向けに「改善アイデア発表会」を企画しました。
最初、若手たちは「え〜無理です」「何を考えればいいの?」と、否定的な反応ばかり。
ところが、「とにかく“失敗歓迎”で、どんな些細なことでもOKです!」と伝えたところ、 徐々に意見が出るようになり、ある女性社員が「コピー用紙の棚の並べ方を変えてみました」と発表しました。

その改善は、劇的な効果はないものの、すぐ実施できる工夫でした。
すると、上司が満面の笑顔で「素晴らしい!」「気づいたことを行動にしたのが最高です」とコメント。
その瞬間、彼女の表情がパッと明るくなりました。
翌週、彼女は別の小さな改善を提案してきました。
さらに翌月、同僚が「私もやってみたい」と参加し始めました。
そう、「ちょっとやってみたら褒められた」 「褒められたから、もう一歩踏み出したくなった」
この連鎖こそが、
ドーパミン→行動→成功体験→自己効力感→さらなる行動
という、成長の好循環の正体です。
ちょっとした「見方」「声かけ」でスイッチは入る
では、職場の中でこのスイッチを入れるには、どうすればよいのでしょうか?
コツは、
「行動の前に褒める」
「プロセスを認める」
「やってみたいことを聞く」
という3つのアプローチです。
「その視点、いいですね!」(=行動前のドーパミン刺激)
「前よりも工夫されていて驚きました!」(=プロセスの承認)
「他にも試したいことってありますか?」(=探求心の喚起)
このようなやりとりが繰り返されるうちに、 部下や若手たちは、「また考えてみよう」「やってみようかな」と自然に動き始めるのです。
しかもこの動きは、上司がいない場所でも、自律的に続くようになります。
なぜなら、それは「やらされる行動」ではなく、「自分で選び取った行動」だからです。
仕事は、学びであり、実験であり、冒険でもある
仕事とは、「登山」に似ています。
高く険しい山に登るには、体力も準備も必要です。
でも、最初からいきなり頂上を目指すのではなく、 まずは近くの低山に登り、「あ、登れたかも」という感覚を得ることが大切です。
その「登れたかも」が、次の挑戦への意欲を育てます。
やがて仲間が増え、少しずつ難易度の高い山にチャレンジできるようになっていきます。
若手や部下が、自分で登る道を見つけ、振り返ったときに「自分で来たんだ」と感じられるよう、 私たちリーダーの役割は、“ガイド”であり、“応援団”であり、“気象予報士”なのかもしれませんね。
その探求心を育てる「バランスの取り方」
さて続いては、こうして芽吹きはじめた「探求心」を、どう育み、どう守っていくか?
つまり、人材育成に必要な“バランスの10視点”について、ご紹介したいと思います。
やりすぎず、怠らず、でも前へ進む。
そんなリーダーの在り方が、きっとそこに見えてくるはずです。
それでは、お話しを続けましょう。
“バランス人材”はこう育てる ― リーダーの10の視点
さて、「ドーパミン」や「自己効力感」という脳科学・心理学の視点から、 人が自ら動き出すための“スイッチ”について、お話ししました。
では、そうした前向きな芽吹きを「一時的な気まぐれ」で終わらせず、 “継続的な行動”へと育てていくには、どうしたらよいのでしょうか?
そのカギとなるのが、「バランスの感覚」を持つリーダーシップです。
一方的に引っ張りすぎれば依存が生まれ、放任すれば混乱が起こります。
育てるという行為は、まるで糸の張力を微調整する、バイオリン職人のような繊細さが求められるのです。
ここからは、そんな「バランス人材=考えながら動ける人」を育てるために、 リーダーが意識したい10の視点をご紹介いたします。

視点1:目的の共有
「なぜこれをやるのか?」という“意味”を最初に伝えること。
これがあるかないかで、部下の姿勢は大きく変わります。
目的のない作業は、ただの雑務です。
でも、目的を共有すれば、それは「自分も担っているプロジェクト」になります。
若手に「役割を与える」のではなく、「使命を共有する」という視点で、関わってみてください。
視点2:振り返りの習慣化
一回やって終わりではなく、「何がよかったか?何を変えたいか?」を振り返る場をつくりましょう。
ポイントは、「できたこと」に目を向けさせることです。
自己効力感は、成功体験の積み重ねによって強まっていきます。
反省だけで終わらず、「よくやったね」の一言が、明日への力になります。
視点3:小さな挑戦機会の設計
大きな課題は避けたくなるものですが、小さな実験なら挑戦しやすい。
たとえば、朝礼のファシリテーション、3分間の改善提案、企画のたたき台づくりなど、 「これならやってみたいかも」と思える“スモールステップ”を設計してみましょう。
やがて、挑戦することが「当たり前」になる空気が、組織に生まれます。
視点4:安心の“定義”を明確にする
「うちは心理的安全性を大事にしています」
と言う企業は多いのですが、 実際に「安心して話せる場」とはどんな場なのか、その定義が曖昧なことが多いのです。
私が現場でよく伝えるのは、「否定されないこと」=安心ではなく、「対話できること」=安心という考え方です。
正しさの押しつけではなく、意見が違っても「なるほど」と受け止める文化こそが、 安心の本質ではないでしょうか。
視点5:他者視点を育てる問いかけ
「あなたならどうする?」ではなく、「〇〇さんの立場ならどう考えると思う?」という問いを使ってみてください。
他者視点を持つことで、自分の判断を客観視する力が育ちます。
これは、バイアスを避ける思考習慣にもつながります。
若手には、「立場を変える問い」をプレゼントする感覚で、問いを届けましょう。
視点6:意味のある承認
褒めることは大切です。
でも、やみくもな「すごいね!」では伝わりません。
大切なのは、「どこがよかったか」「なぜそれが価値があるのか」を伝えること。
つまり、評価ではなく、意味を添えて承認するということです。
これは、自己効力感を高める“最上級の栄養”になります。
視点7:多様な視点を交差させる場づくり
異なる部署の人と対話する、他社の事例を共有する、年齢の違うメンバーでワークを行う。
こうした「交差点」こそ、学びと探求の宝庫です。
“答えのない時代”に必要なのは、固定された正解ではなく、多様な問いを持つ力です。
交差点をデザインすること。
それが、探求心を引き出す仕掛けになります。
視点8:リフレクションとリーダーの“背中”
リーダーが自らの体験を語ること。
それが何よりの教育になります。
「自分も最初はうまくいかなかったよ」
「失敗して落ち込んだけど、こう乗り越えた」
こういった“等身大の失敗談”は、若手にとって最高の学びの教材です。
「背中で見せる」だけでなく、「言葉で渡す勇気」も大切にしていきたいですね。
視点9:余白を大切にする
忙しさで、ぎゅうぎゅうのスケジュールでは、内省も探求も起こりません。
敢えて「ちょっと手を止める時間」「何もしない日」「振り返りノートの時間」を作ることで、 考える力に“呼吸”が生まれるのです。
余白は甘えではなく、成長のための「空気のような存在」。
その余白を意識的に“確保する力”が、今の時代のリーダーに求められています。
視点10:対話によって「問い」を育てる
最後に、最も大切な視点として、「問いの文化を育てる」ことをお伝えしたいと思います。
若手が探求心を持つとは、つまり「自分なりの問いを持つ」ことです。
「何が正解?」ではなく、「どうすれば良くなる?」 「正しいかどうか?」ではなく、「面白いと思うか?」
そんな問いを、日々の対話の中に滲ませていくこと。
それが、バランス人材を育てる、もっともシンプルで効果的な道だと私は信じています。
「支柱をつけすぎた苗は、風に耐えられない」
野菜の苗を育てるとき、支柱を立てて補助することがあります。
でも、その支柱をあまりにも固く、強く、完全に固定してしまうと、苗は風に耐える力を失います。
育てるとは、「倒れないように支える」ことではなく、「自分で踏ん張れるように仕向ける」ことなのです。
あなたの支柱は、若手の可能性を伸ばす“しなやかさ”を持っているでしょうか?
バランスを整えるのは、まず“自分自身”から
ここまで、部下や若手を育てるための10の視点をご紹介してきました。
けれど、もっとも大切なのは――リーダー自身が「バランスを持った人間であること」かもしれません。
続いては、そのことをテーマに、あなた自身が「楽しみながら育つ」存在になるにはどうしたらいいかを考えていきたいと思います。
楽しく成長する組織へ、リーダーが最初にやるべきこと
あなたは最近、心から「楽しい」と感じた瞬間がありますか?
大人になると、「楽しさ」を口にする機会が減っていくように思います。
でも、不思議なもので、人は“楽しい”と感じているときにこそ、一番成長しているんです。
これは、脳科学でも証明されています。
ポジティブな感情が生まれるとき、脳内ではドーパミンが分泌され、「もっとやってみたい!」という意欲が自然に湧き上がります。
さらに、
「誰かとつながっている」
「一緒に笑えた」
「わかってもらえた」
と感じたときには、 オキシトシンという“つながりホルモン”が放出され、心の温度が高まっていきます。
だからこそ、私はこう断言したいのです。
「楽しく学び、楽しく働く組織」こそが、最も強く、しなやかで、育ち合う組織であると。
「楽しさ」は、未来への約束
“楽しい”という感覚は、その瞬間だけの感情ではありません。
楽しかった記憶は、未来の行動を変えます。
あのとき、思いきって発言してよかった
あの研修、笑ったな
でも、心に残ってるんだよな
上司のひと言で、自分って認められてるんだって思えた
これらの記憶は、“脳の報酬系”に刻まれ、次の挑戦を後押しするトリガーになります。
「楽しく学ぶ」という体験は、リーダーシップやスキルではなく、その人の“人生における意思決定”に影響を与える力を持っています。
だから、リーダーであるあなたが“楽しむ姿”を見せることは、何よりも価値あるリーダーシップ行動なのです。
変化の連鎖は、あなたから始まる
ここまで読んでくださったあなたなら、きっと、こう感じているのではないでしょうか。
「たしかに、自分がどう関わるかがカギなんだな」
「じゃあ、何から始めればいいんだろう?」
答えは、実はとてもシンプルです。
それは
「まず、自分自身が楽しんで学ぶ姿を見せる」こと。
・新しいことに目を輝かせてチャレンジする
・わからないことを素直に質問する
・学びの中で自分自身が成長する喜びを言葉にする
こうした姿勢は、あなたの周囲にオキシトシンの“あたたかい感染”を広げていきます。
「うちの上司が楽しそうに学んでた。なんか、かっこよかったんですよ。」
そんな言葉が若手から出てきたら、それはもう、あなたがチームの空気を変えた証拠です。
「笑いながら本気で学ぶ」――そんな場があります
私はこれまで、年間延べ3400人を超える方々と、リーダーシップや人材育成の現場で、ご一緒してきました。
その中で、確信していることがあります。
それは、「真面目に、でも深刻になりすぎないこと」の大切さです。
大人だって、学ぶことは楽しいんです。
心が動けば、笑いが生まれ、仲間意識が生まれ、行動が生まれます。
たとえば、研修中に「問いかけワーク」で爆笑が起きたかと思えば、 その直後に「あの一言、ちょっと泣きそうでした」と真顔で語る受講者がいる。
その場には、ドーパミンとオキシトシンが共に流れている。
「ただの学び」ではなく、「人生がちょっと変わるような体験」がある。
そういう場づくりを、私は本気で続けています。
いま、この瞬間から変わり始める
最後に、あなたに小さな問いを贈らせてください。
「あなたのチームで、次に“楽しく学び、笑い合える瞬間”をつくるとしたら、どんなアクションを起こしますか?」
・朝礼で、ちょっとした問いかけを投げてみる
・“失敗話”を笑いながら共有してみる
・「最近、どんなことにワクワクしてる?」と聞いてみる
どれかひとつでも、やってみようと思えたなら、 あなたの中で、もうすでにスイッチは入っています。
そして、もし…
「この感覚、チームみんなで共有したい」
「一度、坂田さんの研修を受けてみたい」
「うちの若手や管理職にも、この“楽しみながら育つ”体験をさせたい」
そう思ってくださったなら、それはとても光栄なことです。
ぜひ一度、声をかけてください。
あなたの組織の「成長の物語」、その第1章をご一緒できたら嬉しいです。
未来は、予定ではなく、意志でつくられます。
あなたの意志が、きっと周囲の人の意志を動かし、組織を動かします。
ここまで読んでくださったあなたへ、心からの敬意と感謝を込めて
「自ら楽しみ、学び、育つ」リーダーの未来を、私は全力で応援しています。
また、どこかでお会いできる日を楽しみにしています。
それでは、次回コラムでお会いしましょう。
バイバイ!


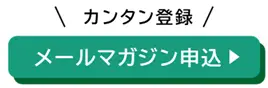 毎週月曜日に「改善ファシリテーション」をテーマとしたコラムを更新、
毎週月曜日に「改善ファシリテーション」をテーマとしたコラムを更新、
火曜日にメールマガジンを配信しております。是非ご登録ください。(ご登録は無料です)

体験セミナーのお申し込みはこちらから
お気軽にお問い合わせください

国内外において、企業内外教育、自己啓発、人材活性化、コストダウン改善のサポートを数多く手がける。「その気にさせるきっかけ」を研究しながら改善ファシリテーションの概念を構築し提唱している。 特に課題解決に必要なコミュニケーション、モチベーション、プレゼンテーション、リーダーシップ、解決行動活性化支援に強く、働く人の喜びを組織の成果につなげるよう活動中。 新5S思考術を用いたコンサルティングやセミナーを行い、企業支援数が190件以上及び年間延べ3,400人を越える人を対象に講演やセミナーの実績を誇る。