参加者の心のシャッターを開く“鍵” │ 話す技術は、聴く力から始まる

伝えたいことと、聞きたいことの“あいだ”を埋めるということ
「坂田さんのお話って、なんかスッと入ってきますよね」
セミナーや講演の後に、そう言っていただくことがあります。
とても嬉しいですし、正直、少し照れくさい気持ちになります。
でも、私はこう思っています。
すっと入ってきたのは、私の話が上手だったからではありません。
むしろ、「聞いてくださった方の中にある“聞きたいこと”と、私の“伝えたいこと”が、たまたま重なった」
そんな奇跡のような瞬間だったのではないか、と。
ですから私は、この“あいだ”をどう埋めるかを、何よりも大切にしています。
一方通行の言葉に、違和感を覚えることはありませんか?
皆さんは、こんな経験ありませんか?
セミナーや講演に参加したとき、
「内容は立派だった。でも、心には残らなかった」
そんなふうに感じたことが、一度や二度ではないのではないでしょうか。
私はあります。
たくさんあります。
そして、そう感じるとき、たいていは「聞きたいこと」と「話していること」がズレているのです。
話し手は、自分の知識や経験を熱く語ってくださっている。
けれど、聞いている側は、心のどこかでこう思っているのです。
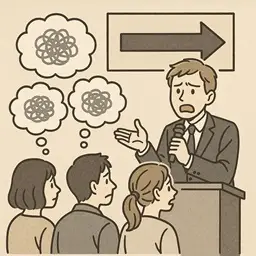 「いや、そこじゃないんです……」
「いや、そこじゃないんです……」
「もう少し、その話を深く聞きたかった……」
「私が知りたいのは、違う角度からの話なんです……」
私も講師をする身として、こうした“受講者側の感覚”を忘れないようにしています。
そして、つい自分も同じように一方的に語っていないか?
そう自問することが、とても大切だと思っています。
聞きたいことは、案外言葉になっていません
セミナーや講演のテーマは、主催者から提示されます。
「問題解決力を高めたい」
「自律的な人材を育てたい」
「モチベーションを上げたい」
どれも大切なテーマです。
でも、その言葉の裏側には、もっと具体的でリアルな“現場の悩み”があると感じることがよくあります。
たとえば、過去にこんなことがありました。
ある会社で「問題解決」をテーマにした講演を依頼されました。
私は論理的思考や構造化、PDCAなどの技術をしっかり組み立ててお話ししました。
ところが、講義後に参加者の一人からこんな感想をいただいたのです。
「坂田さん……自分たち、そもそも“何が問題か分からない”んですよ」
その一言が、ズシンと響きました。
私は、「問題解決の方法」を一生懸命伝えようとしていました。
でも、参加者はそれ以前に、「問題を見つける力」に困っていたのです。
ギャップを埋めるために、私は“拾う”ことをしています
私の講義には、台本がありません。
もちろん、全体の構成や伝えたいメッセージは準備しています。
けれど、話す内容や順番は、その場で決めています。
なぜかというと、参加者の皆さんの反応を見ながら、“あいだ”を埋める必要があるからです。
私は、セミナー中にこういったことを観察しています。
ノートに書かれたキーワード
隣同士の会話のトーン
うなずきの速さ、眉間のしわ
グループワークの中で誰が話しているか
そういった細やかなサインを“拾って”います。
そして、「この人たちは、ここで引っかかっているんだな」と感じたら、 予定していた内容を飛ばしてでも、そこを深掘りしてお話しするようにしています。
それは、構成よりも“つながり”を優先しているからです。
ニーズに応えるのではなく、潜在的な問いを引き出す
人は、自分が何を聞きたいのか、実はうまく言葉にできないことが多いです。
「やる気が出ない」
「どうしたら部下が動くか分からない」
といった表面的な悩みの奥には、 もっと深い“問い”が眠っていることがあるのです。
ですから、私はこう意識しています。
「目の前の言葉に反応するのではなく、 その奥にある“聞きたくても言えていないこと”に応える。」
そして、その“聞きたくても言えないこと”が浮かび上がってくるように、 私はストーリーやメタファーを使って、受講者の心の検索窓に言葉を届けるようにしています。
伝えることより、“届くこと”を目指して
「伝える」と「届く」は、似ているようで違います。
一方的に話すことは、伝えているように見えます。
でも、相手の心の中に届いていなければ、ただの情報の通過です。
私が目指しているのは、言葉が届いて、何かが動き出すこと。
そのために、「聞きたいことと、話したいことのあいだ」を丁寧に観察し、 ときに構成を崩してでも、“いま必要な話”を選び取るようにしています。
部下に、仲間に、上司に、あるいはお客様にあなたが話をするとき
「この言葉は、伝えたいことですか?」
「それとも、聞きたいと思ってもらえることですか?」
この2つが重なったとき、 言葉はただの説明ではなく、行動につながる力になります。
その“あいだ”を埋める工夫、あなたは意識していますか?
「聴くこと」から始まる講師の仕事
「講師は、話すのが仕事ですよね?」
そう思われる方が、きっと多いと思います。
もちろん、そうです。
私たちは人前に立ち、言葉を紡ぎ、伝える仕事をしています。
けれど私は、話す前に“聴くこと”を大切にしている講師でありたいと思っています。
むしろ、こう言ってもいいかもしれません。 「話す技術は、“聴く力”から始まる」と。
話しながら、私は“聴いて”います
ちょっと不思議に思われるかもしれませんね。
「話す」と「聴く」は反対の行動に見えるかもしれません。
けれど、私は話しながら、ずっと“聴いて”いるんです。
たとえば、こんな風に。
前のめりでノートを取っている方がいれば、何をメモしているかをこっそり見る
グループワークで、言葉に詰まった人がいれば、その空気を感じ取る
講義の途中でふっと目をそらす瞬間、その方の中に浮かんだ「問い」を想像する
小さな笑い声やうなずきのタイミングから、どこに共感が起きたのかを読み取る
こうした「見えない声」に耳を傾けながら、私は話す順番や内容をその場で再構成しています。
そうです。
私は、話しながら聴き、聴きながら話しているのです。
メモの片隅に、宝物が眠っている
セミナーの最中、私は参加者のメモに目をやることがあります。
もちろん覗き込むわけではありませんが、ふと視界に入るキーワードや矢印。
そこには、その方の“いま、頭の中で起きていること”が表れているんです。
たとえば
「部下の気持ち=まだ知らない」
「自分の上司がこれを読んだら怒るかも(笑)」
「3ヶ月ルール→うちの棚に当てはまる!」
こんな走り書きを見つけた瞬間、私は心の中で「よし」と小さくガッツポーズをします。
なぜなら、その方の中に“自分ごと化”が起きている証拠だからです。
そして、その言葉をきっかけに、私は話す内容を深めたり、別の例を追加したりします。
「反応」は、言葉より雄弁に語ってくれます
言葉にされない声を聴くこと。
それは、講師にとってとても大切なスキルです。
たとえば、こんな場面があります。
ある参加者がグループ内でずっと黙っている
ワーク中に急に表情が硬くなった方がいる
「分かります?」と聞いたときに、ふと空気が止まる
これらは、すべて“まだ声になっていない反応”です。
私はそこに、「本当に聞きたかったことがここにあるかもしれない」というヒントを感じます。
だから私は、ときどきこう話しかけます。
「今の話、どう思われましたか?」
「これ、皆さんの現場だと、どんな感じでしょう?」
「もし、“そうじゃない”って思った方がいたら、ぜひそれを大事にしてくださいね」
こうした問いかけによって、少しずつ相手の「中にある言葉」が動き出します。
そして、それが“あいだを埋める”糸口になるのです。
聴く姿勢には、安心感が宿ります
人は、「自分の声を聴いてもらえそう」と感じたとき、 自然と心の中の扉が開きはじめます。
それは、脳科学的にも説明がつくことです。
信頼感や共感が生まれるとき、オキシトシンというホルモンが分泌されます。
このホルモンは、ストレスを和らげ、人との結びつきを深めてくれます。
つまり、“聴く姿勢”を示すだけで、場が和らぎ、言葉が届きやすくなるのです。
私はセミナーの冒頭に、「今日の話がすべて正解とは限りません」とお伝えしています。
その一言で、参加者の方は、少しリラックスされるようです。
正解探しではなく、“問いを共有する空間”をつくる。
それもまた、聴く講師の役割だと思っています。
話す講師より、“届く講師”をめざして
私は講師という仕事を20年以上続けていますが、 正直に言って、「自分の話は完璧だ」と思ったことは一度もありません。
むしろ、いつも手探りです。
会場の空気を感じながら、目の前の方に語りかけながら、
「この話、伝わっているかな」「本当に今、この話でいいのかな」と自問自答しています。
でも、そんな中でも、こう思うのです。
話し手の“揺らぎ”があるからこそ、 聴き手との“つながり”が生まれるのではないか。
だから私は、話す力以上に、聴く力を育て続けていきたいと思っています。
あなたは、何を聴いていますか?
あなたが誰かと話をするとき、 部下に指示を出すとき、 お客様に提案をするとき、 家庭で誰かと向き合うとき
その言葉の裏側にある、“本当の声”に気づいていますか?
「この人、いま何を考えているだろう」
「何かを言いたいけど、何を言えていないんだろう」
「どんな問いを抱えているんだろう」
そんな問いを持ちながら接するだけで、 あなたの言葉は、ぐっと“届く言葉”に変わっていくはずです。
次に話すそのとき、どうか“耳”だけでなく、“心”でも聴いてみてください。
ストーリーテリングは、届ける誠意
「坂田さんの話って、まるで自分のことのように感じました」
セミナーや研修のあと、そんな感想をいただくことがあります。
私はいつも、その言葉をとても大切に受け取っています。
なぜなら、それこそが、私が話すうえで最も大切にしている「届ける感覚」だからです。
ストーリーは、心を動かす“かたち”です
私は、ただ理論やノウハウを伝えたいのではありません。
それらを「相手の心に届くかたちで伝える」ことに、意味があると思っています。
そのときに欠かせないのが、ストーリーテリングという技術です。
ストーリーテリングとは、単にエピソードを語ることではありません。
感情を伴った体験のように話すことで、聞き手の中に“疑似体験”を生み出す手法です。
たとえば、ある現場で起きた失敗談を、情景や会話も交えて語ると、 聞き手は、自分がその場にいたかのような気持ちになります。
実はこのとき、脳内では“ミラーニューロン”という神経細胞が活性化しています。
これは、人の行動や感情を見たり聞いたりするだけで、まるで自分が体験しているかのように反応する仕組みです。
だからこそ、ストーリーを聞いた人の中には、
「あの話、自分に重ねて考えてしまいました」 「その状況、うちの職場にもあります」 といった感想が生まれるのです。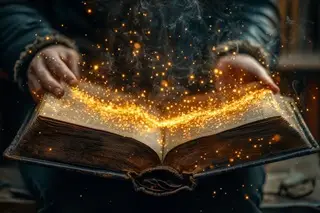
ストーリーは、“問い”を生みます
人は、ただ情報を与えられただけでは、なかなか動きません。
けれど、ストーリーによって心が動くと、“問い”が生まれます。
「もし自分だったらどうするだろう?」
「あの場面、どう対応すればよかったんだろう?」
「これって、私にも起きてることかもしれない」
こうした問いは、強制されて出てくるものではありません。
感じたからこそ、自然にわき起こる“内側の声”なのです。
私は、その“問い”が立ち上がった瞬間に、 初めて「話す価値が生まれた」と感じます。
ですから私は、セミナー中にもこう問いかけます。
「これ、皆さんの職場ならどうなると思いますか?」
「似たような体験、ありませんか?」
「もし自分がこの主人公だったら、どう感じるでしょう?」
こうした問いによって、参加者の中で“自分ごと化”が始まるのです。
これが、ストーリーテリングの最大の力だと私は感じています。
成功談よりも、等身大の“揺らぎ”を
ストーリーといっても、私はあまり“成功体験”を語りません。
むしろ、自分の失敗や悩んだこと、迷ったことを語ることが多いです。
たとえば、
かつて、ある企業でのセミナーで、参加者の反応が極端に薄く、 まったく手ごたえを感じないまま90分が過ぎたことがありました。
私の中では、「ああ、完全に外したな……」という気持ちでいっぱいでした。
でも、終了後に一人の方が、こう声をかけてくれました。
「今日、何も話さなかったんですが、実は心の中でいろんなことが動いてました。 いつも“元気で明るく話す「坂田さんの」迷いながら話していた姿”が、逆に沁みました。」
あのときの言葉は、今でも私の支えになっています。
人は、完璧な話ではなく、揺れながらも進もうとする姿に共感するのだと思います。
だからこそ、私は自分の中の“揺らぎ”を、あえて話すようにしています。
ストーリーテリングは、誠意です
「ストーリーテリングって、テクニックですよね?」
そんなふうに言われることもあります。
確かに、構成や描写の技術はあります。
でも、私はこう答えます。
「ストーリーは、届けたいという“誠意”のかたちなんです」
ただ知識を語るのではなく、 相手の心に届くように、形を変えて渡すこと。
それは、単なる話術ではなく、相手への思いやりの行為だと思っています。
ですから私は、日々の中で「ストック」しています。
現場での体験、何気ない会話、失敗した瞬間、笑いが起きた出来事……
それらを、“いつか誰かの役に立つ日が来る”と信じて、心に残しておくようにしています。
あなたの言葉は、届いていますか?
もしあなたが、部下やチーム、あるいはクライアントに向けて話す立場であるなら、 ぜひ一度、自分の中の「ストーリーの引き出し」を開けてみてください。
「自分が経験した“忘れられない場面”は何だったか?」
「そのとき、どんな気持ちになったか?」
「その体験から、どんな学びがあったか?」
それを思い出すことができたら、 あなたの言葉は、知識ではなく“共感”として届くはずです。
そして何より、相手の心に問いを生み、 行動へとつながる“きっかけ”になるのではないでしょうか。
あなたの語る物語は、 誰かにとって、明日を変えるヒントになるかもしれません。
アイスブレイクとラポール
~場を温め、心を開く技術~
私は、講演やセミナーを始める前の最初の5分間を、とても大切にしています。
話の中身ではなく、“空気”の方です。
なぜなら、この5分間で参加者との「関係性の質」が決まってしまうからです。
どれだけ良い内容を準備しても、 「この人の話、ちゃんと聴こう」と思ってもらえなければ、意味がありません。
ですから私は、本題に入る前に“聴いてもらえる状態”をつくるよう、心がけています。
そのための工夫のひとつが、アイスブレイクとラポール形成です。
アイスブレイクの目的は、場の「緊張」を「安心」に変えること
「アイスブレイク」と聞くと、軽い雑談や笑いを取るテクニックのように思われがちですが、 本質はもっと深いところにあります。
私が目指しているのは、 “講師と参加者”という立場の壁をゆるめること。
そして、“この場に居ていいんだ”という感覚を広げることです。
たとえば、こんなふうに話しかけることがあります。
「今日、初めてこの会場に来た方、多いですよね。私も初めて来たとき、迷いました(笑)。こういうとき、ちょっと緊張しますよね。」
このような、ちょっとした共感から始まる一言は、 参加者の緊張をゆるめる“スイッチ”になります。
脳科学的には、こうした共感や笑いによってオキシトシンが分泌され、 信頼やつながりの感覚が高まりやすくなるのです。
「私とあなた」「あなたと仲間たち」~二重のつながりを意識しています~
私がアイスブレイクで意識しているのは、 二つの“つながり”を生み出すことです。
① 講師(私)と参加者(あなた)のつながり
これは、一方通行の「教える・教わる」関係ではなく、 “この人なら話を聞いてみたい”と思ってもらえる関係性です。
ですから私は、最初に人としての弱みやリアルな一面を出すようにしています。
たとえば、
「電車乗り間違えて、汗だくで来ました(笑)」
「先ほどお弁当を急いで食べたら、ソースをネクタイにこぼしました(苦笑)」
「今日講師を担当する私は、ちょっと頭部がさみしいんです(失笑)」
こうした小さな自己開示は、「あ、この人も普通の人なんだ」と感じてもらえるきっかけになります。
② 参加者同士(あなたと仲間たち)のつながり
もう一つ大切にしているのが、会場にいる参加者同士の関係性です。
講義に来たけど、隣の人と一言も話していない。
そういう状況って、けっこう緊張感が続きますよね。
ですので、私はこんなワークを挟みます。
「今から10秒間だけ、隣の方と“今日ちょっとだけ楽しみにしていること”を話してみてください」
「今日同じ部署から来ている方、手を挙げてみましょう。違う部署の方と話せたらチャンスですね」
こうしたやり取りで、参加者の間に“場の空気の接着剤”のようなものが生まれます。
これは、心理的安全性を高める土台にもなっていきます。
アイスブレイクの効果は、その後の深まりを決めます
一度、こんなことがありました。
ある企業研修で、冒頭のアイスブレイクで笑いが起き、空気がほぐれたあと、 参加者同士が自然と意見を言い合うようになったんです。
終了後にある方がこうおっしゃいました。
「正直、最初は“今日は黙って座ってよう”と思ってました。でも、最初の5分間で、“話してもいいかな”って思えたんですよね。」
そのとき私は実感しました。
「話してもいいかな」 「ここでなら、心の中を出しても大丈夫そう」
その感覚があるかどうかで、セミナーの深まりはまったく違うものになるのです。
だからこそ、私は“本題よりも、まず空気を整える”ことを大切にしています。
ラポールとは、「あなたの言葉に耳を傾けています」というメッセージ
心理学の世界では、信頼関係のことを「ラポール」と呼びます。
これは、ただの仲良し関係ではなく、“お互いが安心してやり取りできる心理的な橋”のことです。
ラポールが築かれていない状態では、どんなに正しいことを話しても、 「その人の話」として処理されてしまう可能性があります。
でも、ラポールが築かれていれば、たとえ厳しい話でも、 「これは自分のことかもしれない」として受け止めてもらえるのです。
私は、アイスブレイクをただの“雰囲気づくり”ではなく、“橋づくり”の時間だと考えています。

あなたの最初の一言は、どんな空気をつくりますか?
セミナーでも、会議でも、1対1の面談でも。
最初の数分間の空気が、その後の対話の“質”を決めます。
「この人の話、聴いてみよう」
「ここでなら、本音を出してみてもいいかも」
「なんだか、この時間、楽しみになってきた」
こう思ってもらえるかどうかは、冒頭の“ほんの一言”にかかっているのです。
ですから、どうか一度ご自身にも問いかけてみてください。
「私は、話す前に、空気を整えているだろうか?」
「この人が安心できるように、場を温めているだろうか?」
「“聴いてもらえる空気”を、つくっているだろうか?」
たった数分でも、空気を変えられる。
その“場づくりの力”こそが、言葉が届くための最初のステップなのです。
「背中で伝える、空気の読み方」
セミナーや講演を行うたびに、私はいつも“空気”を感じ取ろうと、神経を研ぎ澄ませています。
ただ話すだけでは足りない。
ただ伝えるだけでは、相手の心には届かない。
私が伝えたいことと、相手が聞きたいこと。
この二つの間には、いつも微妙な“隙間”が存在します。
そしてその隙間を埋めるために、私は日々試行錯誤しています。
最近では、私の講演に若い講師や後輩が見学に来ることも増えました。
そんなとき、私は“ある行動”を意識的に行うようにしています。
それは、参加者が書いているノートを、少し覗き込むように目をやったり、 隣り合った受講者が話している小さな会話に、わざと耳を傾けてみせたりすることです。
一見すると、ただの自然な動きかもしれません。
でも実はそれ、“わざとらしいくらいの仕草”でやっているのです。
なぜなら、その場にいる若手講師たちにこう伝えたいからです。
「このくらいしないと、空気は読めないよ」
「相手の思いや声は、そこまで自分から拾いにいかなければ、気づけないんだよ」
もちろん、そんな仕草だけで“空気が読める講師”になれるわけではありません。
でも、伝えたいのは、“姿勢”なんです。
情報は、目の前のスライドにあるわけじゃない。
相手のまなざし、手元の筆記、周囲のざわつき、その一つひとつに、 「聞きたいこと」「わかりにくいこと」「もっと深く知りたいこと」が隠れています。
それを拾い上げてこそ、初めてセミナーが“生き物”になります。
若い講師たちには、私のこの姿がどのように映っているでしょうか。
「いちいちノート覗いてすごいな…」くらいにしか思われていないかもしれません。
でも、いつか彼らが自分で講師台に立ったときに、 その時の私の仕草を、ふと思い出してくれるかもしれない。
「そういえば坂田さん、よくノート見てたな」
「耳を傾けるって、こういうことかもな」
そう思ってもらえたら、本当に嬉しいです。
“教える”とは、“伝える”ことだけではない。
背中で見せること。
態度で表すこと。
空気の中に含ませて感じさせること。
私は、そう信じています。
あなたがセミナーや会議の場に立つとき、 どうか一度、自分がどんな“空気の触れ方”をしているか、意識してみてください。
視線の先。
耳の傾け方。
わずかな沈黙。
その一つひとつが、参加者の心のシャッターを開く“鍵”になるかもしれません。
そして、あなたの背中を、きっと誰かが見ています。
“言葉”以上に雄弁な、その背中を。
本当は、もっとたくさんの方に、直接お会いしてお伝えしたいのです。
でも、それをすべて叶えることは難しい。
それが正直なところです。
だからこそ、今回こうしてコラムに綴りました。
話し方やセミナーの作り方、そして空気のつくり方。
私が現場で大切にしてきた「隙間を埋める」技術と想いを、丁寧にお届けしたつもりです。
それでももし、
「実際に話を聴いてみたい」
「セミナーを開いてほしい」
そんなリクエストをいただけるなら、それは私にとって何よりの喜びです。
ぜひ、コメントやメッセージでお気軽に声を届けてください。
あなたの現場でも、心に残る言葉と空気を、一緒に育んでいきましょう。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

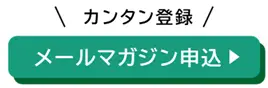 毎週月曜日に「改善ファシリテーション」をテーマとしたコラムを更新、
毎週月曜日に「改善ファシリテーション」をテーマとしたコラムを更新、
火曜日にメールマガジンを配信しております。是非ご登録ください。(ご登録は無料です)

体験セミナーのお申し込みはこちらから
お気軽にお問い合わせください

国内外において、企業内外教育、自己啓発、人材活性化、コストダウン改善のサポートを数多く手がける。「その気にさせるきっかけ」を研究しながら改善ファシリテーションの概念を構築し提唱している。 特に課題解決に必要なコミュニケーション、モチベーション、プレゼンテーション、リーダーシップ、解決行動活性化支援に強く、働く人の喜びを組織の成果につなげるよう活動中。 新5S思考術を用いたコンサルティングやセミナーを行い、企業支援数が190件以上及び年間延べ3,400人を越える人を対象に講演やセミナーの実績を誇る。








