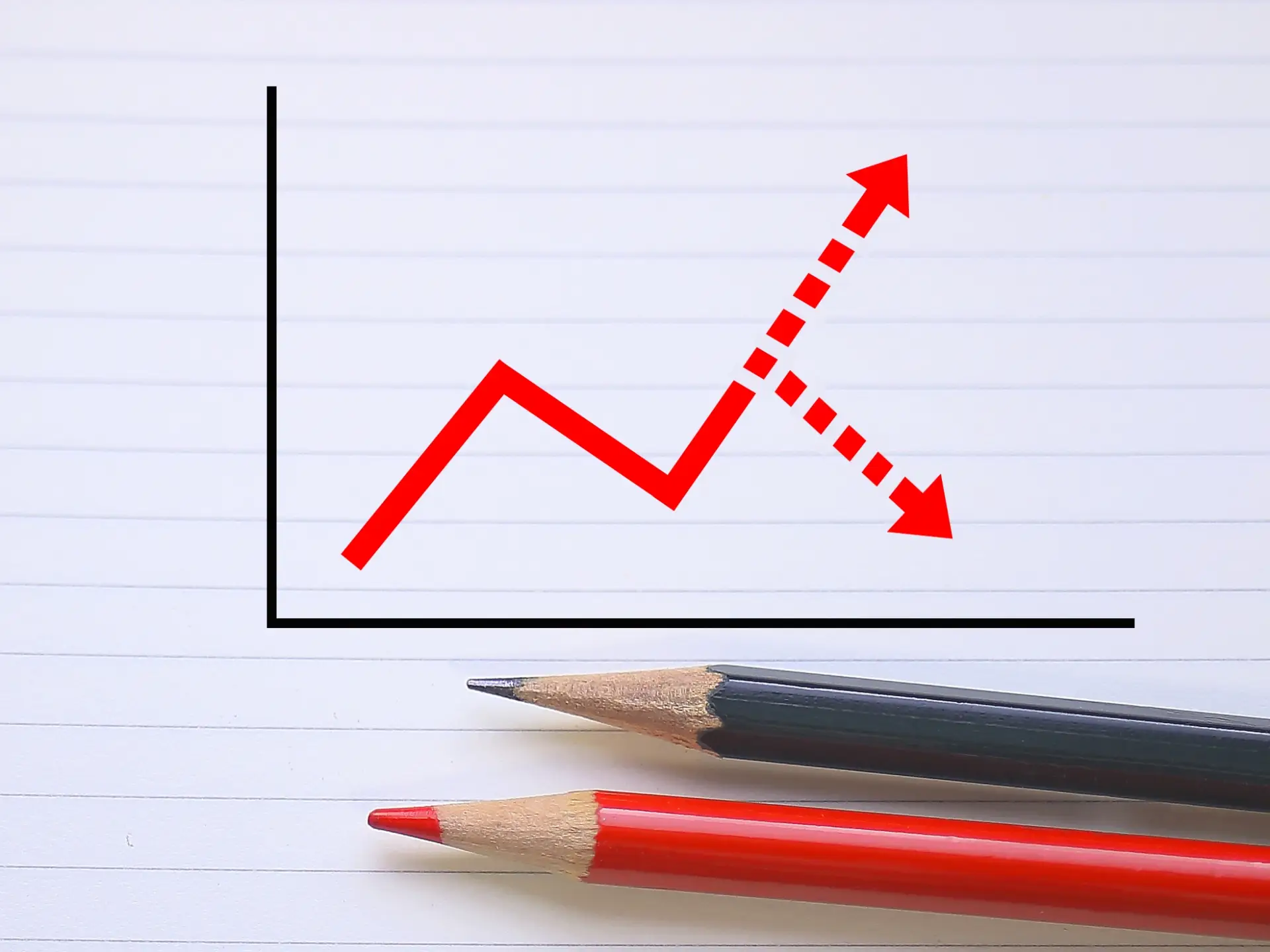【Youtube】新5S思考術 ③ │ 【5S活動】あなたの気づき力は何点?清掃で気づく人材育成~新5S思考術 その3~
※本コラムは、上記動画「【5S活動】あなたの気づき力は何点?清掃で気づく人材育成~新5S思考術 その3~」を要約した内容になっています。
株式会社知識経営研究所(:旧社名・現:株式会社ナレッジリーン)の坂田でございます。
新5S思考術についてのお話をさせていただいております。
前回は、清掃を通じて安全意識や品質意識、保全意識を高めるというテーマについてお話ししました。「意識を高める清掃」という考え方を軸にした内容でしたね。
今回はその続きをお話ししたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
「意識」について
さて、「意識を高める」ということは非常に重要です。
意識があるからこそ、「当事者意識」や「当事者能力」が芽生えてきます。
当事者意識とは、ある物事に対して「自分も直接関わっている」、という認識を持つことを指します。
そして、当事者能力とは、「自分がその物事を解決しなければならない」と実際に行動できる力を指します。
これらの根本はすべて「意識」から始まるのです。
テーマを持って清掃する
テーマを持って清掃を行うことで、多くの「気づき」を得られ、意識が高まります。
例えば、作業中に「無理・無駄・ムラ」に気づくことがあります。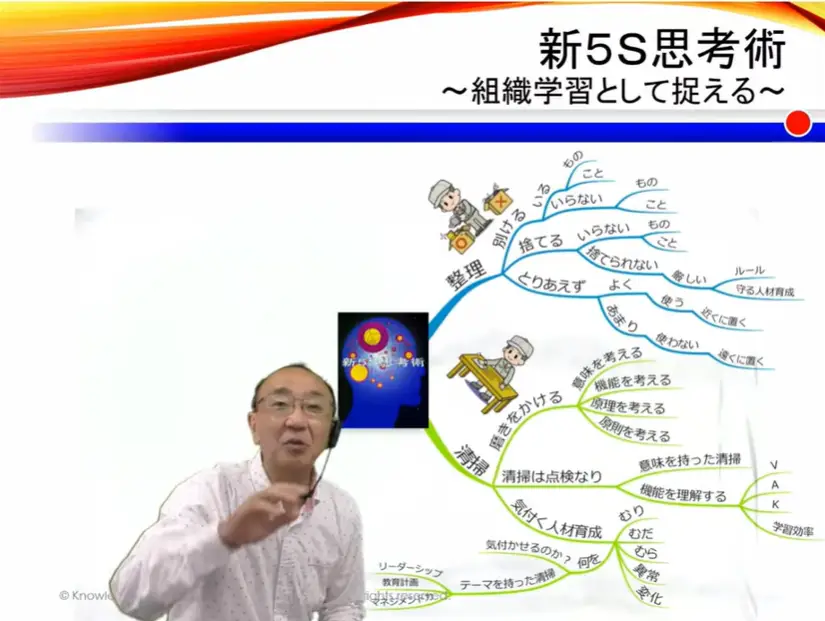
「ここは掃除しづらい」「点検がしにくい」といった改善ポイントや、「昨日までは変色していなかったのに今日は変わっている」などの異常に気づく力が養われます。
清掃中にネジの緩みを見つけて締め直す、塗装が剥がれそうな箇所に注意する、こうした発見が問題意識を高めます。
的確なテーマ設定
清掃には、単なる掃除以上の意味を持たせるべきです。
そのためには、リーダーが的確で適切なテーマを設定することが重要です。
例えば、「最近クレームが増えている」「設備故障が多い」「災害や作業ミスが頻発している」などの課題があれば、それに関連したテーマを設定し、そのテーマに基づいた清掃を行うとよいでしょう。
報告させる
また、部下や後輩が清掃中に異物や異常を見つけた場合、必ず「報告」させるようにしてください。
「報告・連絡・相談(ほうれんそう)」を徹底することで、コミュニケーションが活性化し、彼らが「何か気づいたら報告しよう」という姿勢を育てられます。
その際、報告をしっかりと傾聴し、具体的なフィードバックを与えることが大切です。
逆に、報告を軽視したり冷たく対応すると、報告しようという意欲が失われてしまいます。
清掃時間の工夫
清掃時間についても工夫が必要です。
集中力を保つために、一般的な清掃は15分程度に制限するのが理想です。
もちろん、食品工場さんのように、決められた時間、ルールがある場合はきちんとルールを守りましょう。
短時間でテーマを持って集中して清掃を行い、その中で得られた気づきを共有する。
このように毎日繰り返すことで、意識が高まり、問題検出力が向上します。
これにより、どの部分が掃除しにくいのか、どこに異常が発生しやすいのかといった視点を持つ人材が育成されます。
問題検出力を養う
さらに、清掃活動を通じて「問題検出力」の高い人材を育てることが可能です。
ただ「掃き掃除」「拭き掃除」をするだけではなく、気づきや学びを得られる清掃を行うことで、職場全体の安全性や効率が向上します。
例えば、清掃のしにくい箇所をテーマにすると、そこに潜むリスクや異物の発見につながり、結果として災害の防止や食品安全の向上に役立つこともあります。
VAK(視覚、聴覚、行動)
最後に、「VAK(視覚、聴覚、行動)」を活用したトレーニングについて少しお話しします。
これは、何かを学ぶ際に「見て」「聞いて」「実際にやる」という方法を組み合わせることで、記憶に定着しやすくする手法です。
清掃においても、このVAKを意識してテーマを設定すると、部下や後輩の理解が深まり、意識向上につながります。
今回はここまでとなります。
次回はこの「意識を高めるためのVAK」についてさらに詳しくお話しします。
ありがとうございました。

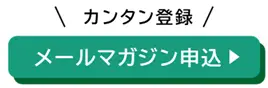
毎週月曜日に「改善ファシリテーション」をテーマとしたコラムを更新、
火曜日にメールマガジンを配信しております。是非ご登録ください。(ご登録は無料です)
体験セミナーのお申し込みはこちらから
お気軽にお問い合わせください