
【無料】「安全意識を高める」体験セミナー│ 労災ゼロを実現する 教育のススメ
定員
ー
参加費
参加費: 無料
参加特典:セミナー後に資料をメール送付
参加条件:終了後アンケートのご回答必須
場所
オンライン研修【Zoom】
株式会社ナレッジリーン(旧 知識経営研究所)は、国や地方公共団体のエネルギーや環境関連の計画・制度設計・運用等に関わる支援及び企業の環境や品質、食品安全、情報セキュリティ、KAIZEN(改善)等に関わるマネジメントコンサルティング・研修等を主業務とするシンクタンク&コンサルティングファームです。

2050年カーボンニュートラルの達成に向けて、世界の気候変動への対応は急激に加速しています。弊社は、民間企業、公共団体問わず、実効性のある計画立案から実行支援、国際的イニシアティブ対応まで、様々なご支援が可能です。
サービスについて知る
社員の専門性を高め、人材を育てる研修・能力開発の支援。豊富なカリキュラムを駆使し、持てる能力を最大に発揮できる人材育成と、活き活きとした職場環境づくりをサポートいたします。
サービスについて知る
会社運営の基盤となる経営管理の仕組みを整え機能させるための、様々な支援をご用意しています。多様化する状況に合わせて、あらゆる規格のご支援を行っています。
サービスについて知る
多種多様な情報が溢れるなか、それらの取捨選択は客観的な視点に基づいたうえで、取捨選択が必要とされます。特に環境分野については、その分野自体が広範なだけでなく、社会・経済との相関性が強いことから、より広範な調査が必要となります。
サービスについて知る
一度構築した仕組みの修正・廃止の判断をするのは、多大な労力が必要とされます。それらの必要性を客観的に評価し、ルールや現場の動きをよりコンパクトに、効率化するためのツールとコンテンツを提供します。
サービスについて知る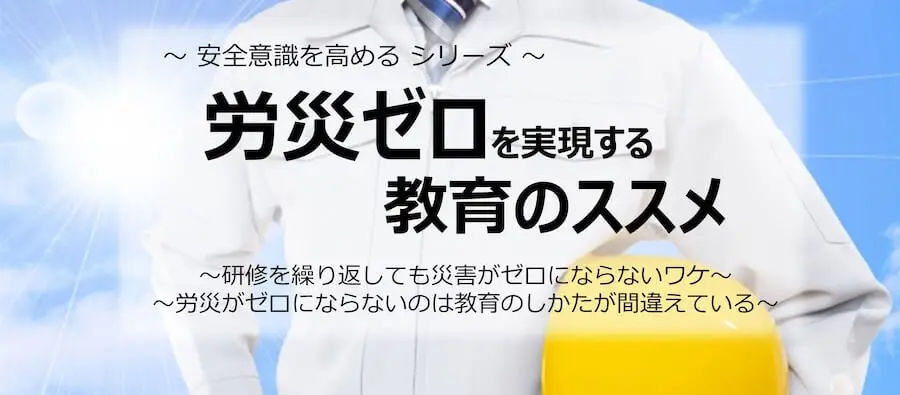
ー
参加費: 無料
参加特典:セミナー後に資料をメール送付
参加条件:終了後アンケートのご回答必須
オンライン研修【Zoom】
(火)
13:30-15:30
受付中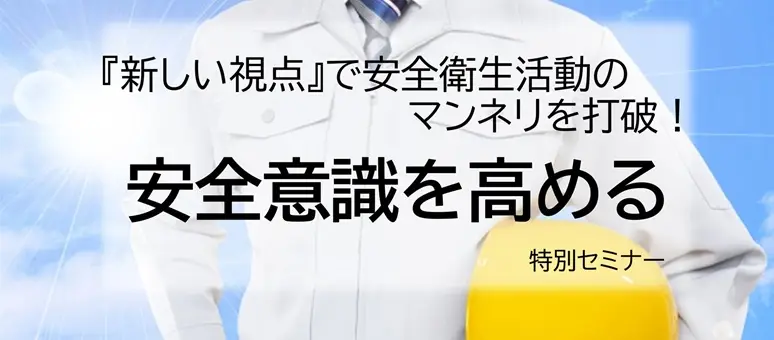
ー
参加費: 5,500円(税込)/1名
※お支払いは銀行振込のみとなります。(請求書を発行いたします)
オンライン研修【Zoom】
(月)
13:30-16:30
受付中
50名
参加費: 無料
参加特典:セミナー後に資料をメール送付
参加条件:終了後アンケートのご回答必須
オンライン研修【Zoom】
(金)
13:30-15:30
受付中 顧客満足に満足せず、
顧客満足に満足せず、ナレッジリーンは、国や地方自治体の受託調査・計画策定業務、
企業に対するマネジメントコンサルティングを主業務としています。
お客様をはじめ仕事に関わる全ての人々と、
自らの進化や変革を楽しみ、喜びをさらに大きくし、
それが実現できたときの感動を共有したいと私達は考えています。
あなたの活躍を期待しています!
